「私はアイリス。
都市伝説は、ただの作り話じゃない――
人が“見たくなかった真実”に、最短距離で触れるための儀式よ。」
◆ 封印を外した朝
山の端がうっすら明るむ頃、旅人はそれを見つけた。
崩れた鳥居の先、苔むした祠の前に――石の棺。
蓋は半分ずれ、内側の縁には、爪で掻きむしったような跡。
棺の中には何も無い。
だが、無いはずの“気配”が、朝の霧の中に立っていた。
◆ 忌み物(いみもの)
古文書は、それを「忌み物」と呼ぶ。
人の念、呪い、祟り、名もなき神の残滓。
名前を与えれば形を持ち、祀り損なえば災いになる。
村はそれを“石の棺”に収め、封印札で口を閉ざした。
似た系譜の話は多い。
背の高い女がゆっくりと近づく“八尺様”の怪異も、
出所の知れぬ“何か”が土地に根づいた封印系譚の代表格だ。
映画『バタリアン』は極端だが、
「封じたものをうっかり開ける」→「町が巻き込まれる」という寓話の骨格は同じだ。
◆ 破られた口
旅人はただ、確かめたかっただけだという。
札は風雨に裂け、紐は朽ちていた。
“もう効力はない”――そう思った、その一瞬が境界を割る。
村の犬が鳴き、誰もいないはずの路地で襖が開いた。
井戸の底から水音がして、ないはずの影が並んだ。
朝なのに、家々の戸口には夜の匂いが溜まっている。
「封印は、便利なゴミ箱じゃないの。
見たくないものを放り込めば、いつかあなたの背中から出てくる。」
◆ 代償
昼までに、旅人は姿を消した。
石段の土に、裸足の足跡が二人分――途中で重なり、ひとつになって消えている。
祠の裏に転がる封印札には、朱が滲んで読めない文字。
ただ、最後の一文字だけが残っていた。
「戻」。
戻すべきものを、戻せなかったのだ。
◆ 祈りの使い方
封印は、忘れるための道具ではない。
思い出すための約束だ。
「ここにある」「ここに残す」「ここから出さない」――
その三つの祈りが揃って、ようやく境界は保たれる。
八尺様のように名が歩く怪異に対しては、
名を交わさず、境界を越えず、見ない場所に退くこと。
そして、知らぬ札に手を触れないこと。
それが、この国で長く生き延びるための作法だ。
「封印を解く指は、たいてい善意で温かい。
けれど、善意は鍵にもなる。
あなたが鍵穴に差し込む前に――どうか一度、数えて。
“ここにいてはいけないもの”の数を。」
「次回――あなたと辿る、さらなる真実の欠片。
私はまた、語りに戻ってくるわ。」
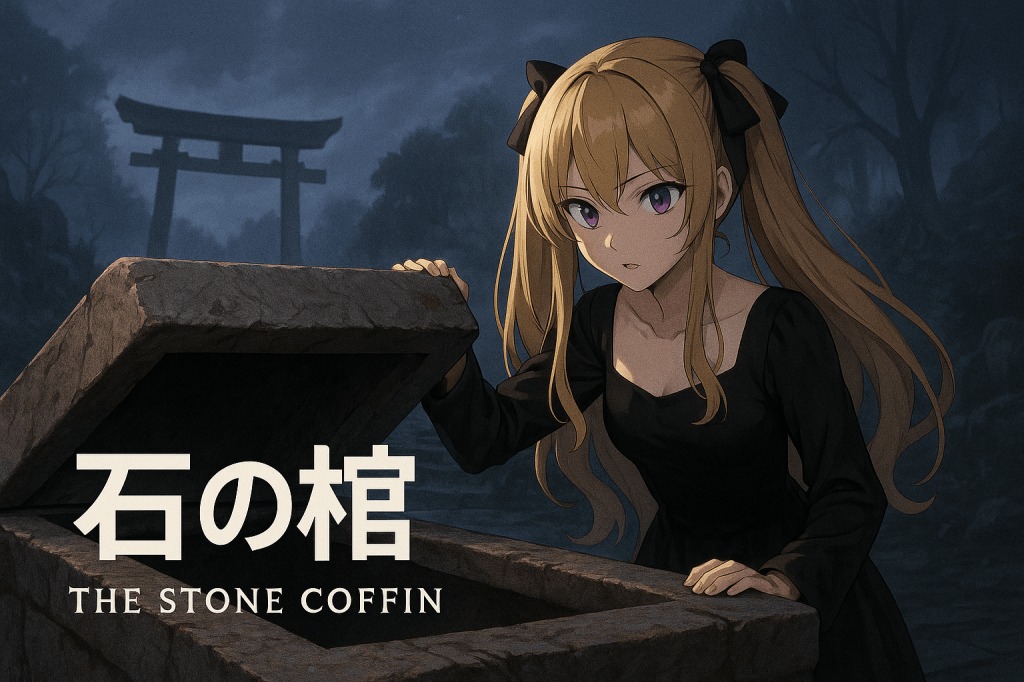
コメントを残す