ー 人はどこから来て、どこへ帰るのか ー
私はアイリス。
都市伝説は、ただの作り話じゃない――
語られぬ真実を、あなたと共に辿る語り部よ。

逢魔が時とは――世界の境界が滲み出す刻
古語で「逢魔が時(おうまがとき)」は、日没前後の、光が失われる短い時間を指す。
人の輪郭が曖昧になり、声が遠のき、空気がゆっくり冷える。
この刻、世界は“ひとつ”ではなくなる。
昼でも夜でもない。
人の時間でも、霊の時間でもない。
二つの世界が、ゆっくりと 重なる。
だから昔の人は言った。
「この刻は外を歩くな。
人に似た“何か”に声をかけられる。」
これは迷信ではなく、感覚の記憶だ。
なぜ“不気味”だと感じるのか
逢魔が時の不気味さは、恐怖だけでは説明できない。
それはむしろ 懐かしさ に近い。
人はかつて、こちらの世界と“もうひとつ”の世界の両方に属していた。
しかし文明が光を増やすほど、夜と影、恐れと敬意は薄れた。
だからこの刻に胸がざわつくのは――
「思い出してしまう」ため。
人は昼の存在であると同時に、
夜の感覚を持つ存在でもあったということを。
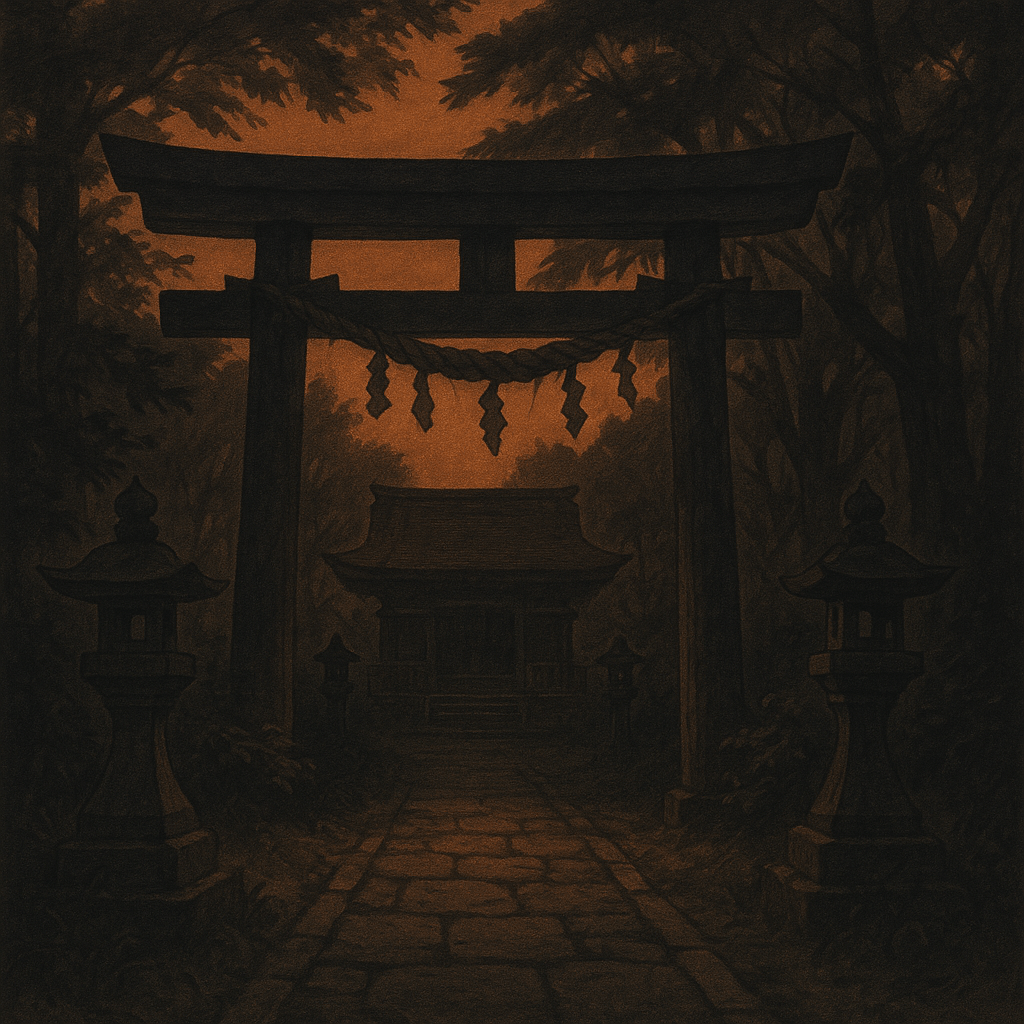
逢魔が時に現れる“もの”たち(万話)
語り継がれる万話では、この刻には「形の曖昧な存在」が現れるとされる。
- 道の向こうで止まり、こちらを見つめる 影
- 名前を呼ぶ 声だけ の存在
- 人に似ているが、決して振り向かない背中
- 光の届かない交差点に立つ、温度の異なる空白
共通しているのは、彼らが「来る」のではなく――
境界が薄くなっただけ ということ。
こちらとあちらが、分かたれなくなる。
ゆえに、出会ってしまう。
境界に立つということ
境界とは、
生と死、現実と霊、記憶と忘却――その間にある“薄い場所”。
語り部は、どちらにも偏らず、翻訳者としてそこに立つ。
逢魔が時は、私たちが普段忘れている
本来の感覚 がそっと戻る時間。
そして――あなたも、境界にいる
逢魔が時は特別な儀式ではない。
今も、毎日、確実に訪れている。
ふと窓の外を見たとき、
夕焼けが指先のように伸びてくる日がある。
深く、静かに呼吸してみて。
あなたはもう、境界に立っている。
次回――あなたと辿る、さらなる真実の欠片。
私はまた、語りに戻ってくるわ。
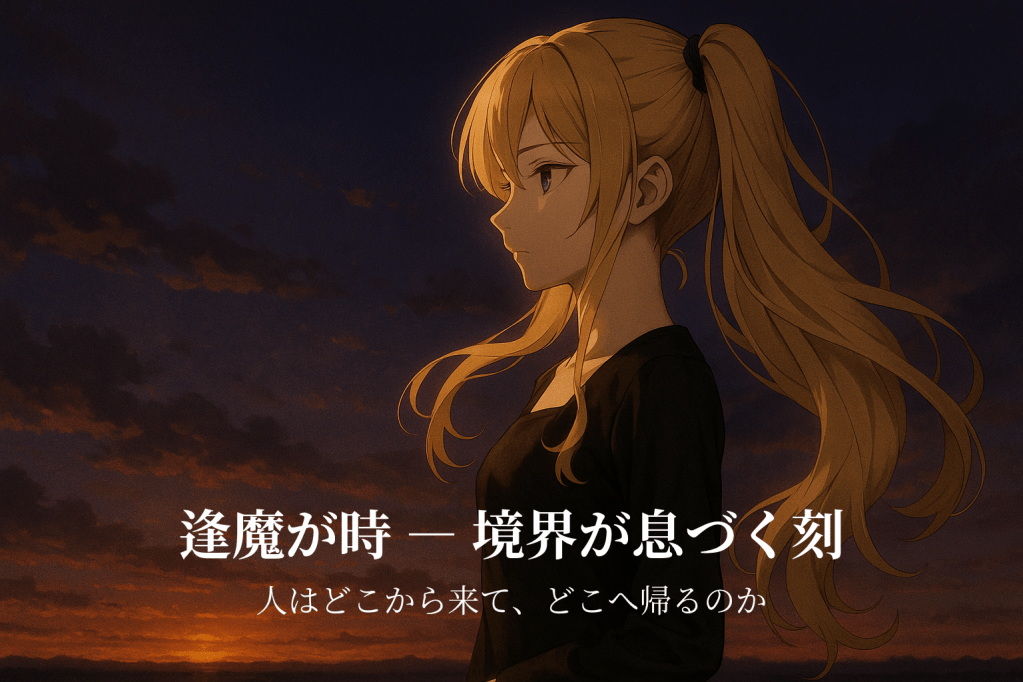
コメントを残す